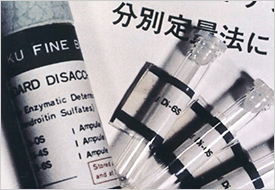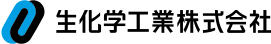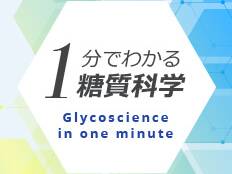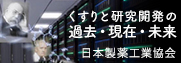生化学工業のおいたちを明らかにしていく上で、避けて通ることができない人たちがいます。水谷當稱(元生化学工業社長)を中心に、江上不二夫博士(元東大教授・元日本学術会議会長)、渋沢敬三氏(元大蔵大臣)、高田利種(元生化学工業社長)の各氏です。この章では、彼らの運命的な出会いの中で、生化学工業の基礎がいかにして築き上げられてきたかを見ていきます。

- 拡大
- 江上不二夫博士
水谷當稱が、複合糖質の構成成分のひとつである、コンドロイチン硫酸について知ったのは、敗戦後間もない昭和22(1947)年、旧制東京高校の同窓生であり、また義兄でもあった江上不二夫博士を通じてでした。
当時、GHQによる戦時中の軍需工場などへの操業停止命令により、水谷が勤務していた三菱重工業川崎機器製作所も、遊休化した機械設備と従業員を抱え、深刻な状況に陥っていました。食糧難、悪性インフレの昂進、殺伐とした世相・・・。その時の体験が、水谷の後の挑戦のベースになっていったのです。
「敗戦によって、資源のない日本は、石油などの原料を輸入しなければならなくなりました。そこで私は、これからは科学技術の振興を図って新しい製品を開発するような仕事、つまり、頭を使って無から有を生ずるような仕事をしたらいいのではないか、と考えるようになったのです。」(水谷談)

- 拡大
- 元社長 水谷當稱
昭和22(1947)年、たまたま名古屋に出張した水谷は、当時名古屋大学教授だった江上博士の家に泊まりました。そして、夕食後、江上博士が頭痛薬の話を始めました。「いま、アセトアニリドという合成の頭痛薬がよく売れているが、この薬には毒性習慣性がある。こういう薬が横行しているのは大変困ったことだ。」「自分は以前から、多糖のひとつであるコンドロイチン硫酸という物質の研究を続けているが、頭痛によく効きしかも副作用が極めて少ない。技術面は全面的に支援するから、ぜひ企業化してほしい。」と熱心に勧められたのです。
水谷は予想外の話の成り行きに驚きましたが、詳しく聞くうちに興味が湧いてきました。博士によれば、「コンドロイチン硫酸は副作用が少なく安全な薬になる。しかも、原料は輸入に頼らず、練り製品を作る時に廃物となって出る鮫の軟骨から抽出できる。また、コンドロイチン硫酸は、人間をはじめさまざまな生物の体内に存在する生体成分なので、研究を進めれば、さらに多くの有用性が出てくるだろう。」というのです。
とはいえ、水谷は文科系出身で糖質科学に関して当時はまったくの素人、しかも新規に医薬品を開発するリスクはきわめて高いものがありました。そこで、水谷は、多くの友人たちに相談しましたが、誰もがこの事業化のアイデアに関心を示し、反対する人はいなかったのです。とくに、高校の先輩で親しかった篠島秀雄氏(元三菱化成工業社長)は大賛成で、「やってみろよ」の一言に力を得た水谷は、ついに挑戦する決意を固めたのでした。

- 拡大
- 昭和25(1950年)4月14日
渋沢敬三邸前にて
後列向かって左より、太田武司(元三河薬品専
務・元当社取締役)、横山半之助(元三河薬品
社長・元当社取締役)、山内勝巳(元当社監査
役)、水谷當稱、杉浦茂左衛門(元当社取締役)
前列向かって左より、渋沢敬三、郷古 潔、
及川古志郎、高田利種
生化学工業の誕生に重要な役割を果たした人物が、渋沢敬三氏です。「日本の資本主義の父」と呼ばれた渋沢栄一氏を祖父に持つ渋沢氏は、日銀総裁や大蔵大臣を務めた財界の巨頭でしたが、民俗学者としても大きな功績を残しています。また、日本の学問の発展を陰で支えた「パトロン」でもありました。
渋沢氏はよく日本の学界における「名コンダクター」と言われます。それは、渋沢氏が、学問という“オーケストラの世界”で、異分野の才能を切磋琢磨させ成長させていく能力に優れていたこと、また、それぞれの人の個性や資質をすばやく見抜き、それを伸ばそうとしたことからです。
そんな渋沢氏と水谷との出会いのきっかけを作ったのは、科学映画製作者として有名な岡田桑三氏(元東京シネマ社長)でした。渋沢氏と親しかった岡田氏は、江上博士の長兄波夫氏(考古学者)とも交遊があり、その関係で水谷とも顔馴染みだったのです。
その頃、水谷は会社勤務の傍ら、コンドロイチン硫酸の研究に取り組み始めていました。しかし、有力な後ろ盾を持たない水谷は、すぐに資金面で行き詰まってしまいました。そんなある日、水谷から話を聞いた岡田氏が、渋沢敬三氏に相談するように熱心に勧め、昭和23(1948)年4月、江上兄弟と水谷の3人は渋沢氏を訪問することになりました。
その日、江上博士からコンドロイチン硫酸に関する説明を聞くと、渋沢氏は「学者からこういう話を聞くのは初めてだ。」と笑い、「副作用の少ない安全な頭痛薬を世に出すことは大変いいことだ。出資者には心当たりがあるし、自分が直接に指導するからぜひやりなさい。」と援助を約束してくれました。
さらに、渋沢氏は「これからの日本はもっと学問を尊重し、学者を優遇する世の中にしなくてはならない。」「こういうことは大会社にはやらせない。」「これまでの日本はとかく最終の販売者が大いに儲けるにもかかわらず、生産者、発明者が下積みとなりがちであったが、この薬関係の事業では、発明者、生産者、販売者の順に尊重する理念で経営を進めなさい。」と、企業化に関する指針まで示してくれたのです。
水谷は、渋沢氏の言葉に感激し、これから先どんな苦難があろうとも、この事業をやり抜くという固い決意をこの瞬間に固めたといいます。もし、この時の渋沢氏との出会いがなければ、現在の生化学工業はありませんでした。渋沢氏との出会いは、それほど運命的なものだったのです。
ペリーが4隻の黒船を率いて上陸したことで知られる神奈川県横須賀市久里浜を拠点に、興生水産株式会社が誕生したのは、及川古志郎氏(元海軍大臣)の発案からでした。及川氏は、戦争体験から日本人の体格やスタミナが欧米人に比べ劣っていることを痛感し、食事をデンプン中心からタンパク質や脂肪中心に切り替えるべきと考えていました。さらに、事業を起こし、元軍人たちに職を提供したいという思いもありました。
及川氏が、そうした考えを同郷の郷古潔氏(元三菱重工業会長)らに相談し、興生水産を立ち上げたのは、昭和22(1947)年のことでした。郷古氏から新会社を指導するには、さらに渋沢敬三氏に相談すべきとの意見が出て、両氏が渋沢邸を訪問したところ、二人の先輩からのご依頼であれば引き受けざるを得ないとの回答を得ることができました。
この新会社の経営実務を託されたのが、元海軍少将高田利種です。高田は早速、久里浜の旧海軍基地跡を払い下げてもらい事業を開始しました。最初は好調だったものの、冬になると水揚げがなくなり、会社の事業としては不安定なことがわかってくると、高田は漁業に見切りをつけます。次に、水産加工に取り組みますが、これも素人の悲しさで失敗の連続でした。高田は活路を見いだすために何をすべきか、暗中模索を続けていました。
高田に転機を与えたのが渋沢氏でした。この時、渋沢氏の頭には、水谷のコンドロイチン硫酸という事業シーズと、興生水産の資本・人・設備を合体させる構想がひらめいていたのです。すでに渋沢氏は、三河薬品という製薬会社を、共同開発のパートナーとして水谷に紹介していましたが、同社工場の爆発事故という予期せぬ事態の発生により実現できずにいました。そこで、今度は大胆にも、製薬業とは無縁の興生水産と、薬品化事業を結びつける“仲人”役を買って出たのです。
渋沢氏から、頭痛薬開発事業を勧められた高田は、当初自分には製薬業はできそうにないと断りました。しかし、度重なる渋沢氏の勧めと、及川氏の同意を受け、ついにコンドロイチン硫酸の開発に取り組む決心をしたのです。一方、水谷の方は、三河薬品との共同開発計画が中止になり、一時は目の前が真っ暗になる思いでしたが、渋沢氏から興生水産を紹介され、ようやく研究に没頭できる場所を得ることができました。
こうして、不思議な巡り合わせから、渋沢氏によって絶妙のタイミングで引き合わされた高田と水谷は、長年にわたりコンビを組み、生化学工業という新しい企業体を創っていくことになったのです。渋沢氏は、コンドロイチン硫酸という事業の“種”と、興生水産という“器”とを組み合わせ、互いに補い合う理想的な関係を創ったのです。まさに「名コンダクター」としての渋沢氏の面目躍如といえます。